
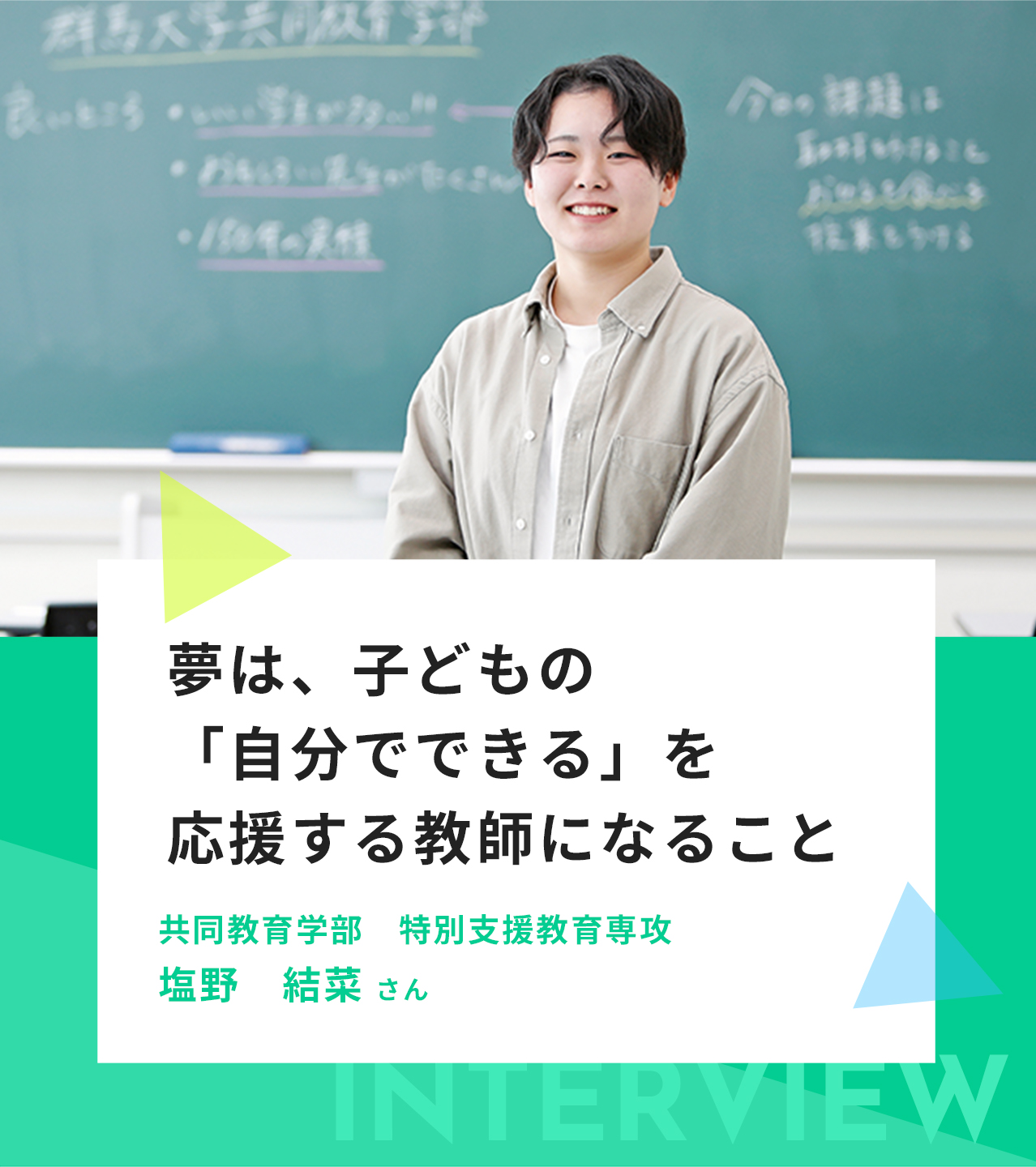
夢は、子どもの
「自分でできる」を
応援する教師になること
共同教育学部 特別支援教育専攻
塩野 結菜 さん
教師と障がい者支援の両方を叶えたくて群馬大学へ

物心ついた頃から障がい者支援にずっと興味がありました。保育園の同級生に障がいのある子がいて、その子は私たちと同じ小学校ではなく、特別支援学校に行くと知ったのです。てっきりまた一緒に通えるのだと思っていただけに衝撃を受けた記憶があります。「障がいがある子たちは、私たちとは違う学校に行かないといけないのか」と幼いながらに思うところがあり、そこから障がいのある子たちの支援をしてみたいと思ったことがルーツだと思います。高校生になった頃には学校の先生にも憧れており、教師になる夢と障がい者支援のどちらも叶えられる特別支援学校の先生を目指すことにしました。
群馬大学の共同教育学部は、教育実習や教員採用試験の対策も手厚いことで知られています。また、特別支援学校教員免許の5領域(知的障がい、視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、病弱)全てを取得できること、さらに聾学校教員に欠かすことのできない日本手話の技術を学べるのが、群馬大学の特別支援教育専攻です。より専門性の高い教師になりたい私にとって最適な環境だと実感しています。
特に思い出深い講義は「日本手話と日本語の違いを学ぶ」です。この講義では、1年次から日本手話を文法から丁寧に学び、手話通訳の技術を身につけていきます。3年次には、実際に「福祉サービスの窓口」という場面を想定して手話通訳を行ったり、美術館に赴いて学芸員さんの解説を通訳したりしました。話す日本語との違いは難しく大変でしたが、日本手話の奥深さを知り、とても充実していた講義でした。手話は手先だけでなく表情も大事で、眉の動きで疑問などを区別したり、目の開き方で文法が変わったり、上半身全体を使った会話です。難しいですが、身につければ一生モノのスキルだと思います。アルバイト先に来られた聴覚障がいの方を手話でご案内したこともありますし、教育現場に限らず役に立てるので嬉しいです。

自閉症児とのふれあい、支援を目的とするサークルにも所属しています。地域の施設をお借りし、一緒に遊んだり、学習の支援を行います。今私が支援しているお子さんは、出会った当初三輪車に乗れなくて、親御さんも乗れるようになって欲しいと希望されていたので遊びながら三輪車の練習をしていました。教育実習後、久しぶりにその子と会ったら、三輪車を乗りこなしていたんです。少し見ない間に成長していることが嬉しかったですし、その子が頑張った足跡が垣間見えて感動しました。時に意思の疎通がうまくいかないこともありますが、その子のペースに合わせて常に寄り添ってあげることを心がけています。
今後は教師になる夢を叶えるべく、教員採用試験や卒業論文の作成に力を入れていきます。小・中学校どちらにも教育実習に行った中で、特別な支援を必要としている子は多いと感じました。特別支援学校だけに限らず、全ての子どもに寄り添って、自分でできる自信をつけてあげられるような先生になりたいです。
※この画面の情報は、全て取材した時点のものになります。
